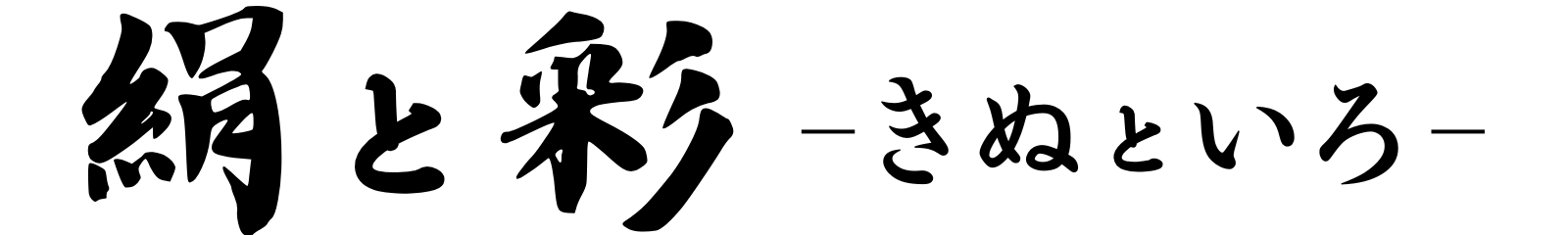結婚式やパーティーのお呼ばれ、子どもの行事、不祝儀など人生の節目には着物を選ぶ機会がたくさんあります。しかし着物には種類がたくさんあり、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
着物を着る上で「どの場面で何を着るか?」のマナーを知っておくことはとても大事です。
この記事では様々なシーンで着るべき着物についてくわしく解説します。それぞれのシーンに合わせた着物の選び方やマナー、コーディネートのポイントまでご紹介します。
結婚式・披露宴
結婚式・披露宴では、立場によって着るものが異なります。
花嫁・親族・お呼ばれゲストに分けて見ていきましょう。
花嫁
結婚式では白無垢、披露宴では色打掛や引き振袖を着ます。
白無垢

色打掛

引き振袖

白無垢は結婚式における花嫁の正礼装で、白一色に統一された着物です。白には「純潔」や「新しい門出」を象徴する意味があり、古くから神前式や仏前式で着用されています。
色打掛は白無垢に続く格式高い婚礼衣装。鮮やかな色や豪華な柄が施され、披露宴やお色直しで着用されます。
引き振袖は振袖の一種で、最も格式が高い着物の一つです。一般的な振袖とは異なり、地を引きずるほどの長さが特徴。打掛に比べて動きやすく、お色直しの衣装として選ばれることも多いです。
親族
親族が着る着物は、新郎新婦との関係や既婚か未婚かによって異なります。
- 新郎新婦の母・祖母:黒留袖
- 新郎新婦の姉妹:既婚の場合は黒留袖や色留袖、未婚の場合は振袖
- 新郎新婦の叔母・伯母:黒留袖や色留袖
- 新郎新婦のいとこ:色留袖
黒留袖

色留袖

振袖

黒留袖
黒留袖は黒い生地に5つの家紋が入り、裾に絵羽模様(えばもよう)が施されています。既婚女性が結婚式で着用する第一礼装であり、最も格式高いとされています。
黒留袖には、金銀の刺繍や箔が施された豪華な袋帯を合わせます。帯揚げや帯締め・小物類も格式高く、金銀や白の上品なデザインを選びましょう。
黒留袖は新郎新婦の母親や祖母、既婚の姉妹、既婚の叔母・伯母が着用します。
色留袖
色留袖は既婚・未婚問わず着用できる着物で、紋の数によって格式が決まります。五ツ紋が入った場合は黒留袖と同格の第一礼装になります。
花や鶴、松竹梅などの縁起物が描かれるデザインが多く、フォーマルな場面にふさわしい品格と華やかさを添えます。
色留袖は夫婦の姉妹や叔母・伯母、いとこなどが着用します。
振袖
振袖は未婚女性の第一礼装であり、華やかさと若々しさを演出します。
結婚式で振袖を選ぶ際は、花嫁の衣装の色とかぶらないように注意しましょう。
また、花嫁が引き振袖を着る場合は、振袖のランクを落とすのがエチケット。
振袖は、袖の長さによって「小振袖」「中振袖」「大振袖(本振袖)」に分けられますが、親族は中振袖を着るのが一般的です。
お呼ばれゲスト
結婚式・披露宴のお呼ばれで気をつけたいのが「着物の格」。自分が新郎新婦の友人・同僚・遠縁の親戚等の場合は、親族より着物の格を下げるのがマナーです。
最適な着物は訪問着や付け下げ。未婚・既婚問わず着られますし、留袖や振袖に比べると格が下がるため、お呼ばれにおすすめです。
訪問着

付け下げ

訪問着は柄がつながっており、広げたときに一枚の絵のように模様続きになっている着物。ゴージャスな印象を与えるため、結婚式やパーティーなどのフォーマルな場に適しています。
お祝いの席では上品で明るい柄を選び、帯や小物も華やかなものを合わせます。
付け下げは訪問着よりも柄が控えめな着物で、裾や袖、胸や肩の部分にバランスよく描かれています。品の良い華やかさがあり、略礼装として用いられます。
フォーマルな場では華やかな帯、小物を選ぶことで格式を調整できます。
成人式(二十歳のつどい)
成人式(二十歳のつどい)では振袖を着ます。
振袖は袖が長く、大きく揺れることから「未婚女性の清らかさ」「親元を離れて羽ばたく若さ」を象徴しています。

振袖は袖の長さによって3種類に分けられます。
- 長さ約104~120cmの「大振袖(おおふりそで)」
- 長さ100cm前後の「中振袖(ちゅうふりそで)」
- 長さ約85cmの「小振袖(こふりそで)」
袖が長いほど格式が高いとされており、成人式では「中振袖」を選ぶことが多いです。
着物に描かれている柄にはさまざまな意味があります。
桜は門出や豊かさ、菊は不老長寿、梅は逆境に耐える強さや気高さ、牡丹は高貴・富、椿は気取らない美しさ、扇は末広がりの発展や繁栄を表し、手鞠は人生が丸く収まり順調にいくようにという願いがこめられています。
不祝儀(通夜・葬儀・告別式)
お通夜やお葬式などで着る「着物の喪服」には、正喪服・準喪服・略喪服の3種類があります。
- 正喪服:背中と後ろ袖、両胸に五つ紋の黒喪服
- 準喪服:寒色系の無地に三つ紋、または一つ紋の着物
- 略喪服:寒色系の色無地や江戸小紋に三つ紋や一つ紋、または紋なしの着物
紋の数が多いほど格式が高くなります。
しかし着物の喪服にはマナーがあり、誰もが着用するものではありません。立場によって着るものが異なります。
親族と一般参列者に分けてみていきましょう。
親族
喪主や遺族、親族が着物を着る場合は、正喪服を着用します。
ただし、親族の中でも正喪服を着るのは2〜3親等までとされるのが一般的です。

正喪服には合わせる帯や小物、着方にもマナーがあります。
| 黒紋付 | 背中と後ろ袖、両胸に染め抜きの五つ紋が入った黒紋付 |
|---|---|
| 黒喪帯 | 黒一色で飾りのないものか、雲取りや流水、紗綾形などの織り帯 |
| 長襦袢・半衿・足袋 | 白無地 |
| 帯揚げ・帯締め・草履・バッグ | 光沢のない黒 |
帯結びは不幸が重ならないように一重太鼓で、お太鼓は小さく低めにします。
参列者
現代では通夜・葬儀などの場面においては洋装が多く、着物で参列すると人目を惹きつけてしまったり、親族や他の参列者に華美な印象を持たれることがあります。
そのため、一般参列者であるときは着物を着用していくことは避けた方が無難でしょう。
ただし、地域や親族によって喪服に対する風習・考え方は異なります。
その点をふまえ、着物で参列する必要がある場合の喪服について解説します。
親族以外の参列者は、遺族よりも格の高い喪服でないほうがよいとされています。
そのため、亡くなった方が友人・知人や同僚、遠縁の親戚の場合は、準喪服または略喪服を着用します。

準喪服
準喪服は「黒喪服×色喪帯」「色喪服×黒喪帯」の2パターンがあります。
- 「黒喪服×色喪帯」黒の三つ紋または一つ紋の着物にグレー・紫・紺などの色喪帯
- 「色喪服×黒喪帯」グレー・紫・紺など寒色系の色無地で三つ紋または一つ紋の着物に黒喪帯
どちらも長襦袢・半衿・足袋は白無地を選び、帯揚げ・帯締め・草履・バッグは黒を合わせます。
略喪服
略喪服は「色喪服×色喪帯」。
グレー・紫・紺など寒色系の色無地で三つ紋または一つ紋の着物に色喪帯を合わせます。
着物は江戸小紋の鮫、角通し、行儀など控えめな柄であれば色喪服の代わりに着用しても問題ありません。
他の喪服同様、長襦袢・半衿・足袋は白無地、帯揚げ・帯締め・草履・バッグは黒を合わせます。
式典・パーティー
式典やパーティーに着物で出席する場合は、色留袖や訪問着、色無地を着ます。
どれを着るかは、式のフォーマル度や自分の立場によって異なります。
色留袖

訪問着

色無地

色留袖は裾周りにのみ絵柄が入っている着物で、既婚・未婚問わず着られる準礼装です。家紋がつくことで格が高まります。
フォーマルな式典など格式が求められるときに適しています。
訪問着は模様が肩から裾にかけて途切れなく続く「絵羽模様」が特徴の着物です。家紋を入れると格が高まり、既婚・未婚問わず着用できます。
華やかな装いが求められるパーティーに向いています。
色無地は、生地を一色に染めたシンプルなデザインの着物です。「地紋」と呼ばれる織り模様が入っているものと、入っていないものがあります。
地紋の種類や家紋の数、合わせる帯によって普段着から礼装まで様々なシーンで着用できます。
式典やパーティーで着る場合は、華やかで明るい色合いのものや光沢があり地紋が浮き出ている色無地がおすすめです。
子どもの卒業式・入学式・七五三・お宮参り
子どもの行事で着物を着るときに気をつけたいのが「母親は引き立て役」ということ。
主役は子どもですので、母親はシーンに応じた着物を選びつつ控えめな着こなしを心がけましょう。
卒業式
卒業式は厳かな式典であるため、落ち着いた色調の訪問着や付け下げ、一つ紋入りの色無地が向いています。
訪問着

付け下げ

色無地

訪問着は着物を広げたときに一枚の絵のように模様続きになっている着物、付け下げは柄が控えめで裾や袖、胸や肩の部分にバランスよく描かれている着物です。
訪問着や付け下げの場合は、地色と柄のコントラストが控えめなものを選びましょう。葵・藤・牡丹・菖蒲などの柄を選ぶと季節感が出ます。
一枚持っていると重宝する色無地も、紋を入れれば卒業式に着ていくことができます。淡い寒色系や濃紺、若いママなら淡いピンクや若草色などもおすすめ。
帯は金糸・銀糸が入ったフォーマル向けの袋帯を選び、二重太鼓を結ぶのが基本です。派手にならないようし、帯揚げや帯締めで着こなしを工夫しましょう。
入学式
入学式も卒業式同様、訪問着や付け下げ、一つ紋入りの色無地が適しています。
訪問着

付け下げ

色無地

春の訪れを感じさせる淡いピンクやクリーム色、ミント色、淡い水色、ラベンダーなどの明るい地色で落ち着いた絵柄を選びましょう。
卒業式と入学式で同じ着物で出席してもマナー違反ではありません。
その場合は帯の柄や色味を変えたり、帯揚げや帯締めを変えることで、同じ着物でも雰囲気を変えることができます。
七五三
七五三は子どもの成長を祝う晴れの場であるため、訪問着や付け下げが適しています。
訪問着

付け下げ

色無地

吉祥文様や草花模様など、子どもの健康や成長を祈る意味合いの柄が好まれます。
とはいえ、主役は子どもですので華美になりすぎない落ち着いた色合いや、淡く明るい色のものを選びましょう。
また、色無地や江戸小紋を着用しても構いません。
シンプルなデザインは、主役の子どもを引き立てるのにピッタリ。お祝いの席にふさわしい、明るい色合いのものがおすすめです。
お宮参り
お宮参りでは祖母が留袖、母親は訪問着や付け下げ、色無地を着用することが一般的です。
色留袖

訪問着

付け下げ

赤ちゃんの初着を引き立てるため、母親の着物は落ち着いた色柄のものがよいでしょう。
格式の高い神社に参拝する場合は、家紋入りの訪問着が適しています。
初詣
訪問着

振袖

小紋

初詣は新年の始まりを祝う場でありつつも、着物の着用ルールやマナーはないため、比較的自由な装いが楽しめます。
神社で正式参拝をする場合は訪問着や振袖、家族や友人とリラックスして初詣に行く場合は小紋など、目的や同行者に応じて選びましょう。
新年らしい紅白やゴールド、松竹梅、梅や鶴といった縁起の良いモチーフを取り入れると◎。
観劇
観劇に着ていく着物は、劇場の雰囲気や演目の内容、観客としての立場に応じて選ぶのがポイントです。
訪問着

付け下げ

小紋

訪問着は歌舞伎やオペラなど、格式のある観劇に最適。金糸や銀糸を使った袋帯で華やかさをプラスしたり、パールや控えめな色の帯締め・帯揚げを合わせて上品にまとめるのがおすすめです。
ミュージカルや現代劇など、格式を求められない観劇には付け下げがよいでしょう。柄が控えめで上品なため、品格のある装いができます。
カジュアルな雰囲気の観劇や軽いコンサートなら小紋。柄合わせで個性を出したり、明るい色や季節感のある帯揚げ・帯締めで楽しい雰囲気のコーディネートもOKです。
お稽古
お茶などのお稽古で着物を着るときはルールやマナーが求められます。
- (お茶の場合)主役は茶道具、あくまで人間はわき役なので華美なものは避ける
- 後染めのやわらか着物を着る、紬や絣などかたい着物は不向き
- 場の格、立場に応じて着物を選ぶ
色無地

訪問着

小紋

まず一枚持っておきたい着物は色無地。季節を問わず着用できる上、帯や小物の合わせ方でセミフォーマルに格上げすることもできます。
格のあるお茶会に参加するときは、訪問着や付け下げで華やかに装いましょう。織りの袋帯と礼装用の小物を合わせます。
普段のお稽古なら小紋でも構いませんが、柄物を着る場合は季節に合わせた柄を選びましょう。茶道は季節感を大切にしていますので、少し先取りするくらいが良いとされています。
食事会
食事会にふさわしい着物は、食事会の内容や会場の格式によって異なります。
フォーマルとカジュアルに分けて見ていきましょう。
フォーマルな食事会(ドレスコードあり)
ドレスコードがあるレストランや料亭、ホテルなどでのフォーマルな食事会では、訪問着や付け下げがおすすめです。
訪問着

付け下げ

どちらも袋帯を合わせて格式高い装いにしましょう。
華やかなお食事会なら色柄も華やかに、落ち着いたレストランなどでのお食事なら色柄を控えめにするなど、食事会のフォーマル度によって着物の色柄を調整するとベストです。
花柄の場合は季節外れにならないように注意しましょう。
カジュアルな食事会
友人や家族との気軽な食事会なら小紋や紬がよいでしょう。
小紋

紬

小紋は全体に同じパターンの柄が繰り返し描かれている着物、紬は素朴な風合いが特徴の着物です。
小紋も紬も普段着なので、コーディネートに制限はありません。色柄や小物によって季節感や雰囲気を楽しむことができます。
小紋は柄の豊富さを活かして「華やかさ」や「遊び心」を表現したいときにぴったり。紬は素材感を活かして「落ち着き」や「ナチュラルさ」を表現したいときに向いています。
観光・旅行
観光や旅行で着物を着るなら小紋や紬がおすすめです。
小紋

紬

おしゃれ着として親しまれている小紋は、軽くて動きやすいため観光にもぴったり。洗えるポリエステル素材のものを選ぶと、汗をかいても安心です。
紬は肌触りが良く通気性がよいため、観光で長時間着ていても快適に過ごせます。また、丈夫な生地でシワになりにくいため、持ち運びにも便利。
どちらの着物も柄の種類が豊富ですので、自分の好みや行く場所に合わせて選びましょう。
観光や旅行のときは、動きやすく座るときにもストレスが少ない半幅帯(はんはばおび)がおすすめです。長く歩く観光には、クッション性のある「カジュアル草履」を選ぶとよいでしょう。
花火大会・夏祭り
花火大会や夏祭りでは浴衣を着るのが定番です。
浴衣

絽の着物

浴衣は色柄のバリエーションが豊富で、朝顔・花火・水紋など夏らしい柄も多く、イベントの雰囲気をより楽しむことができます。軽くて通気性が良い綿素材を選ぶとお手入れしやすいです。
帯は半幅帯や兵児帯を選び、華やかでボリューム感のあるリボン結びや変わり結びにするとよいでしょう。
大人っぽい上品な雰囲気を出したいなら、浴衣よりも少しフォーマルな絽や紗の着物もおすすめ。 透け感のある涼しげな素材なので夏らしさを楽しめます。帯や小物を華やかにするとお祭りらしい雰囲気に仕上がります。
まとめ
着物を着るときは、シーンに合わせた着物を選ぶことが大事です。
それぞれのシーンにふさわしい着物は以下のとおり。
| シーン | 着物の種類 |
|---|---|
| 結婚式・披露宴 | (花嫁)白無垢・色打掛・引き振袖 |
| (親族)黒留袖・色留袖・振袖 | |
| (ゲスト)訪問着・付け下げ | |
| 成人式(二十歳のつどい) | 振袖(中振袖) |
| 不祝儀(通夜・葬儀・告別式) | (親族)正喪服 |
| (参列者)準喪服または略喪服 | |
| 式典・パーティー | 色留袖や訪問着、色無地 |
| 子どもの卒業式・入学式 | 訪問着・付け下げ・色無地 |
| 子どもの七五三 | 訪問着・付け下げ・色無地 |
| 子どものお宮参り | (祖母)色留袖 |
| (母親)訪問着・付け下げ・色無地 | |
| 初詣 | 訪問着・振袖・小紋 |
| 観劇 | 訪問着・付け下げ・小紋 |
| お稽古 | 色無地・訪問着・小紋 |
| 食事会 | (フォーマル)訪問着・付け下げ・小紋 |
| (カジュアル)小紋・紬 | |
| 観光・旅行 | 小紋・紬 |
| 花火大会・夏祭り | 浴衣・絽や紗の着物 |
着物選びの参考にしてくださいね。